印刷用ページを表示する掲載日:2011年3月1日更新
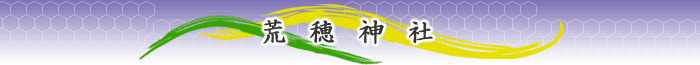

鎮座地
宮脇
祭神
瓊瓊杵尊 ほか六社
由緒が古く、格式も高かった古社。
「日本三代実録」貞観2年(860)の頃に、荒穂天神の名で神階昇叙の記事がみえ、延喜5年(927)撰進の「延喜式」神名帳に社名がみえるいわゆる式内社(肥前国では4社)である。藩政時代は基肄郡上郷総社。明治6年郷社、昭和15年県社。
戦前は基山村(町)産土神社とされていたが、現氏子は第4区・旧第3区の全戸。
祭神については古来諸説があるが、民俗学上は原初は基肄山山頂のタマタマ石を磐座として農耕に恵みを与え豊穰をもたらす自然神・産霊神であると考えられている。
貞享元年(1684)に書き上げの「荒穂神社縁起」においては、中 荒穂大明神、左一 下鴨大神、左二 八幡大神、右一 宝満大神、右二 春日大明神、右三 住吉大明神、以上六社としている。(現在は五十猛命を加えている。)
創建については同縁起は、人皇第37代孝徳天皇の御代(645~654)松津(基肄)国造物部金連の末裔金村臣によるとしている。
社殿は最初、基山山頂にあったが、戦国の兵火にかかって転々とし、現在地に造営されたのは貞享2年である。
現社殿(流れ造り)は、拝殿は文政2年(1819)、社殿・中殿はともに安政5年(1858)の改建になる。
神課は12人であった。
現行祭礼
1月1日元旦祭、2月19日春祭、7月19日夏祭、8月1日茅の輪・人形流し、秋分の日神幸祭。
神幸
江戸時代には祭礼日も多く、神幸は年3回行われていた。現在は年1回秋分の日に行われる。その日未明、神輿・供奉行列は本宮を発ち、御旅所の御仮殿に下る。
ここで正午から神事、続いて芸能が奉納されたあと還幸、夕刻、再び芸能が奉納される。
供奉行列は以前より簡略化されているが、芸能は奉納各地区の人々の誠意と基山町民俗芸能保存会の尽力により、つぎのとおり維持、奉納されている。
災払い(仁蓮時)、風流(西長野)、獅子舞(向平地・引地・辻・田中・一井木・水上)、狭箱、羽熊(不動時・南谷・才ノ上・旧陣屋) 〔供奉〕 楽(木山口)、御鉄砲(秋光・千塔)。
境内社 合祀社
名木・古木
ムクノキ(160年) クスノキ(410年) ヒノキ(260年) ヤマモガシ(110年) ※(樹齢推定)


宗派
真言宗善通寺派
本尊
大日如来(胎内に請来の秘仏不動明王)
当町正応寺集落の人、篠原龍善和尚が、同地にあった阿弥陀堂を大正12年(1923)、昔からの霊地とされる仁恩の瀧の現在地に移したのが前身である。
その後、昭和12年(1937)、現武雄市山内町真手野にあった文明12年(1480)創立という吉祥坊から坊号・本尊を勧請し、寺号を吉祥寺とした。よって龍善和尚をもって吉祥寺中興開山とする。末寺をもち、大本山仁恩之瀧と称する祈祷・信仰寺である。
山紫水明の広い境域に、昭和58年建立の本堂をはじめ、諸堂・神社が配され、霊域公園の景観を現じている。
問合せ
基山町大字園部1167番地(字正応寺)
Tel:0942-92-2128
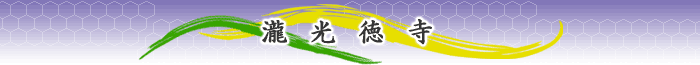

宗派
中山身語正宗
本尊
不動明王(中山不動尊)
宗教法人法によって昭和27年(1952)に立宗した、中山身語正宗の大本山である。
宗祖は当町仁蓮寺集落の出身、覺惠上人(木原松太郎、通称又右衛門のち八坂と改姓)である。立教は大正元年(1912)という。翌年、高野山に登って得度。
大正10年、和歌山県にあった竜福寺の寺号を請来して瀧光徳寺と改め、宮脇荒穂神社後方の地に本堂を建立、昭和6年(1931)、寺谷の現在地に移転した。昭和21年には古義真言宗より分派独立している。
教圏は西日本を主に広域に及ぶ。
広い境域には、木造大建築物をはじめ奥の院廟、大小の諸堂が配され、五重塔がひときわ映える宗教的ふんいきの中に景観も楽しめる。
問合せ
基山町大字宮浦2200番地(字 寺谷)
Tel:0942-92-2931


宗派
光明念佛身語聖宗
本尊
不動明王(中山一之瀧大日大聖不動明王)
木原覺惠上人を開祖、覺法上人を宗祖としている。立教は明治44年(1911)11月7日、木原覺惠父子によるものとしている。
昭和6年(1931)、瀧光徳寺が寺谷に移転し、残された長子の唯一(覺法上人)は、古来の霊地一之瀧に結庵、同15年、本福寺と改称。同25年、高野山真言宗別格本山、のち真言宗泉湧寺派。同51年、同派を離脱して光明念佛身語聖宗を立宗。同52年、宗教法人法による法人となる。
教圏は西日本を主に広域に及ぶ。
筑紫平野を一望におさめる基山中腹の広い境域に、色彩豊かな本道をはじめ諸堂等が配され、平成五重塔が一きわ美しく聳える。
問合せ
基山町宮浦字中山2120番地(字 中山)
Tel:0942-92-2451